「通いの場」の立ち上げ、拡大、多様化、フレイル予防の観点を踏まえた「通いの場」の機能強化について学び、具体的に地域づくりにつながる介護予防活動を進めることができる核となる人材を育成します。
以下のマークは、各研修の開催方法になります。
なお、以下に記載の研修スケジュールは令和6年度のものになります。
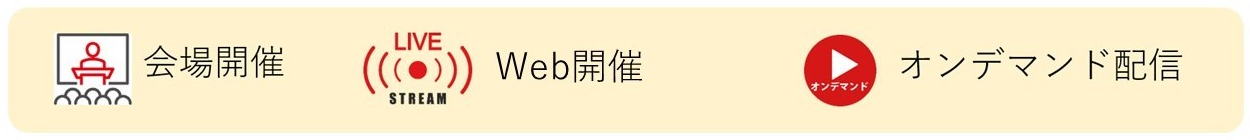
【対象者】
区市町村において介護予防事業を担当する職員(地域包括支援センター職員等を含む)、東京都介護予防・フレイル予防推進員、生活支援コーディネーター、区市町村の介護予防事業に関わる専門職等
【概要】
介護予防・フレイル予防の概論、各論(運動器、口腔・栄養、社会参加、認知機能、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における通いの場の活用)、短期集中予防サービスについて、研究成果を踏まえた根拠に基づく解説や東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター事業の紹介等を行う。
【目的】
介護予防事業を実施するにあたり必要な、介護予防・フレイル予防の基礎知識を習得するとともに、介護予防施策における通いの場づくりの重要性について理解を深める。
【年間計画(予定)】全1回、オンデマンド250名程度
【研修内容】
・介護予防・フレイル予防概論 ・医療的視点から見たフレイル予防
・運動器 ・社会参加
・口腔・栄養 ・認知機能
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における通いの場の活用
・短期集中予防サービス
【対象者】
区市町村において介護予防事業を担当する職員(地域包括支援センター職員等を含む)、東京都介護予防・フレイル予防推進員、生活支援コーディネーター、区市町村の介護予防事業に関わる専門職等
※これから新たに通いの場を立ち上げたり、既存の通いの場に新しいプログラムを導入しようとする方を対象としています。
【概要】
研修を通して、通いの場づくりを戦略的に進めるための取組計画を行い、プレゼン型(住民向けのプレゼンテーション資料の作成)による通いの場立ち上げの手法を学び、計画の見直しを図りながら実際に通いの場立ち上げを推進できるよう、研修を進めます。
【目的】
住民主体の介護予防活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する「地域づくりによる介護予防」の考え方を理解するとともに、通いの場の立ち上げの手法を習得します。
【年間計画】全4回 各80名程度
【研修内容】
全4回の連続研修となります
[第1回]
テーマ「通いの場とは?~地域を把握する~」
・通いの場について
・前年度受講者の発表
・地域の把握
[第2回]
テーマ「通いの場の立ち上げ手法と評価」
・通いの場の立ち上げ
・グループワーク~通いの場の立ち上げ手法~
・通いの場の評価
・グループワーク~評価設計①~
[第3回]
テーマ「通いの場の計画作成と立ち上げ」
・グループワーク~評価設計②~
・プレゼン作成手法
・グループワーク~プレゼン資料の作成~
[第4回]
テーマ「取組の進捗と成果報告」
・受講者発表
・総括
【対象者】
区市町村において介護予防事業を担当する職員(地域包括支援センター職員等を含む)、東京介護予防・フレイル予防推進員、生活支援コーディネーター、区市町村の介護予防事業に関わる専門職等
※すでに通いの場の展開を進めていて、既存の通いの場の多様化や機能の強化を図ることを目的に通いの場づくりに携わる方を対象としています。
【概要】
住民主体、広報、ナッジの視点を踏まえた継続支援や多様なプログラム、多世代共生による通いの場づくり及び運営支援について、ポイントや実例を解説し、実践につながるよう、講演・事例紹介・グループワーク等を実施します。
【目的】
フレイル予防の視点を踏まえた、活動内容の多様化による通いの場の機能強化や、多様な主体との連携による通いの場づくり及び実践的な運営支援の手法を習得する。
【年間計画】全6回、各80名程度
【研修内容】※参加希望の回ごとに受講可能です。
[第1回]
テーマ「住民主体とリーダシップ」
・住民主体の理論と概念
・支援方法や運営のポイント
[第2回]
テーマ「通いの場の広報(チラシづくり)」
・情報発信の考え方の基礎
・チラシづくりの具体的手法
[第3回]
テーマ「ナッジ」
・ナッジの理論の基礎と応用
・実践例
[第4回]
テーマ「ちょい足し・多様なプログラム」
・継続支援の意義とポイント
・ちょい足し・多様なプログラムの実践例
[第5回]
テーマ「男性の居場所」
・男性が参加しやすい環境づくりのポイント
・実践例
[第6回]
テーマ「多世代共生」
・多世代共生による運営のポイント
・実践例
【対象者】
自治体職員及び東京都介護予防・フレイル予防推進員
※介護予防事業に携わり、地域資源の把握や通いの場づくりを中心とした行動計画・評価等を実施する方を対象としています。
【概要】
地域資源の把握、庁内連携やリハ職との連携、通いの場の評価・効果分析等について、介護予防事業に関わる者のうち、特に通いの場づくりを中心とした実務に携わる者向けに、実践的な知見及びスキルを付与する。事例紹介・グループワークを取り入れた内容とします。
【目的】
東京都介護予防・フレイル予防推進員等が、通いの場の拡大・継続支援や、通いの場等におけるフレイル予防の視点を踏まえた予防活動の促進について効果的・効率的に取り組めるよう評価・効果分析の手法を含むスキルを習得する。
【年間計画】全5回、各100名程度
【研修内容】※全5回の連続研修となります。
[第1回]
テーマ「地域づくり・地域診断」
・介護予防の取組・概論
・PDCA SMART活用実践例
・地域資源の把握
・グループワーク:目的の階層化・戦略シート
[第2回]
テーマ「庁内連携・リハ職との連携」
・自治体の計画と情報共有
・庁内・関係機関との連携
・多様な主体~民間企業との連携~
[第3回]
テーマ「PDCAサイクル」
・グループワーク: ロジックモデル
・ペルソナ分析・ステークホルダー
・グループワーク:実行シートの作成
[第4回]
テーマ「評価・効果分析」
評価~通いの場のレベル&事業・行政レベル~
グループワーク:評価
[第5回]
テーマ「取組の進捗と成果報告」
・受講者発表
・総括
【PDCA SMARTの活用】
介護予防・フレイル予防推進員研修では、研修の効果が業務に反映されるようにするために、PDCA SMART(地域アセスメントから評価計画まで一元管理するエクセル版管理システム)を使った計画づくりの講義とグループワークを実施しています。
男性高齢者の孤立化防止やフレイル予防を目的とした右図の記入例では、地域の強みと弱み(課題)を記述し、さらに、最も優先的に取り組むべき課題一つに絞り込み、その課題に対して、目的の階層化の欄では、将来の目指すべき姿から、まずは取り組むべき事までの目的を階層化し記述しています。ロジックモデルの欄では、レベル2の目的と取組(活動・事業)を転記し、レベル3の主たる目的と取組、さらにレベル4の目的を転記することによって、アウトプット及びアウトカムを明記しています。地域アセスメントから、評価までを戦略的に業務で遂行することを可能にします。